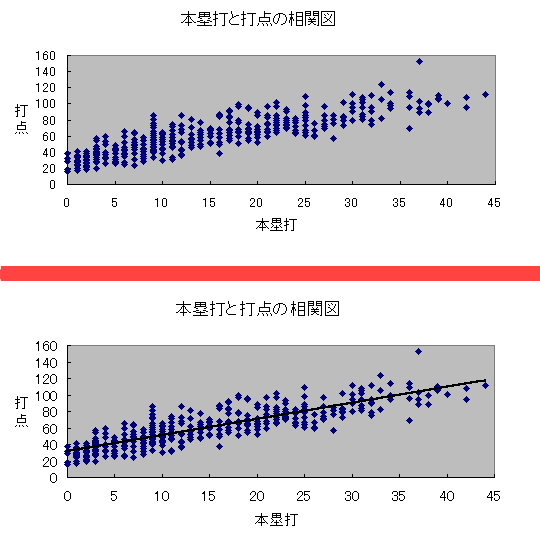第4回 打撃タイトル2冠の相関関係(2001.07.12)
打撃部門のタイトルはご存知のとおり、首位打者、本塁打王、打点王の3つである。
1950年に2リーグに分裂して今年で52年目であるが、3冠王を獲ったのは、南海ホークス・野村克也(1965年)、読売ジャイアンツ・王貞治(1973、74年)、ロッテオリオンズ・落合博満(1982、
85、86年)、阪急ブレーブス・ブーマー(1984年)、阪神タイガース・バース(1985、86年)の5人で計9回しかなく、3冠全てを獲得することがそれだけ困難であることがわかる。
2冠王の頻度とその割合
| 人数 | 回数 | 割合 |
|---|
| 本塁打王&打点王 | 30 | 47 | 45.2% |
|---|
| 本塁打王&首位打者 | 5 | 8 | 7.7% |
|---|
| 首位打者&打点王 | 7 | 7 | 6.7% |
|---|
2冠王は本塁打王&打点王が圧倒的に多く、47回もある。昨年はセ・パ両リーグとも本塁打王&打点王の2冠王が誕生した(巨人・松井秀喜、近鉄・中村紀洋)。ちなみに割合とは、(回数)÷104で算出した数値のことである。104とはもちろん52(年)×2(リーグ)という意味だ。
30人が47回も達成しているだけあって複数回獲得者が王貞治(9回)を筆頭に、野村克也(5回)、中西太、長池徳二、山本浩二、デストラーデ、松井秀喜(いずれも2回ずつ)と続いている。
一方、その他の2冠王は8回、7回と極めて少なく、特に首位打者&打点王は複数回獲得者がおらず、打率が良くてもそれが必ずしも打点に結びつかないことを表していると言えよう。最近では横浜のローズ(1999年)とイチロー(1995年)が達成している。また本塁打王&首位打者を獲得したのはヤクルトのハウエル(平成4年)が最後で、それより前となると王貞治(3回)、中西太(2回)、長島茂雄、大下弘の時代まで遡らなければならない。
普通に考えて、本塁打を打てば打点が増えるし、打率を稼ぎに行けば大振りをしなくなるので本塁打は出にくくなる、というのは当然のこととして捉えて頂けることと思う。ここではそれらのことを視覚化していきたい。
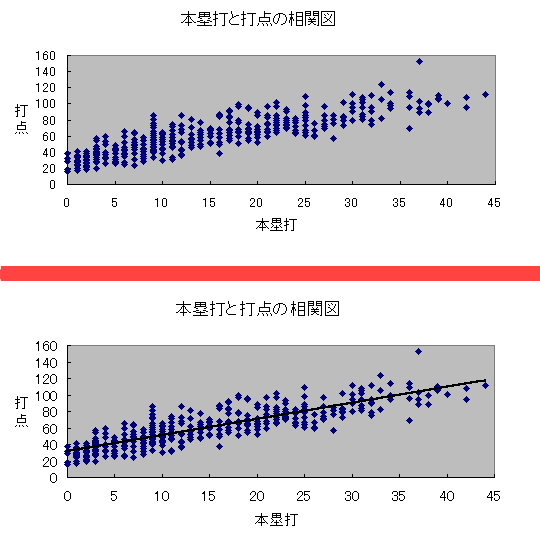
右の図は本塁打と打点の散布図の散布図である。
横軸を本塁打、縦軸を打点とした。例えば、本塁打が10本で打点が40の場合は(10 ,40)の所に点を打つ。これを全選手について繰り返す。つまり中学や高校の数学(一次関数など)で習ったのと同じ要領である。この場合は、本塁打がX軸で打点がY軸と考えてくれれば良い。
元となるデータは、1995年〜2000年までのペナントレースにおいて規定打席に到達した延べ392人分である。図を見ると右上がりに散らばっているのがおわかりいただけると思う。やはり、本塁打が増えれば打点も増えるという考えは正しいと言えることになる。
そこで下の図。下の図は上の散布図に対して近似直線を引いたもので、その直線は横軸をX軸、縦軸をY軸とした時、
Y=1.96X+31.35 と表される。
まあ、このへんの話は統計学の「最小2乗法」になるので詳しい過程は省略する。今では表計算ソフト(Excel)という便利なものがあるので、データさえ入力してしまえばこれらの処理はすぐに行われる。
この式(直線)が意味するのは、本塁打をX本打った時に、Yの値が打点の平均値として期待される、ということである。つまり、
X=0の時 Y=31.35
X=10の時 Y=50.95
X=20の時 Y=70.55
X=30の時 Y=90.15
X=40の時 Y=109.75
となり、平均すると本塁打0本の選手は打点が31.35で、本塁打40本の選手は打点が109.75にあることを示しているのである。なお、相関係数は0.866である。
一方、その他の2冠についてであるが、グラフを作成したものの、ただ点が散らばっているだけで全く規則性が見られなかったので掲載は省略した。
やはり過去のデータが表しているように本塁打王&打点王以外の2冠王はなかなか出にくいようである。巨人の松井も現在、課題であった打率面では上位をキープしているが、本塁打と打点がいまいちで(マークがきついから仕方がないのだが)3冠王獲得はまだ先のことになりそうだ。そう考えると、3冠王を達成した打者たち(特に3度達成し、「ヒットだけなら4割打てる」と豪語した"オレ流"落合)に改めてその凄さを感じてしまう。
プロ野球記録回顧部屋に戻る