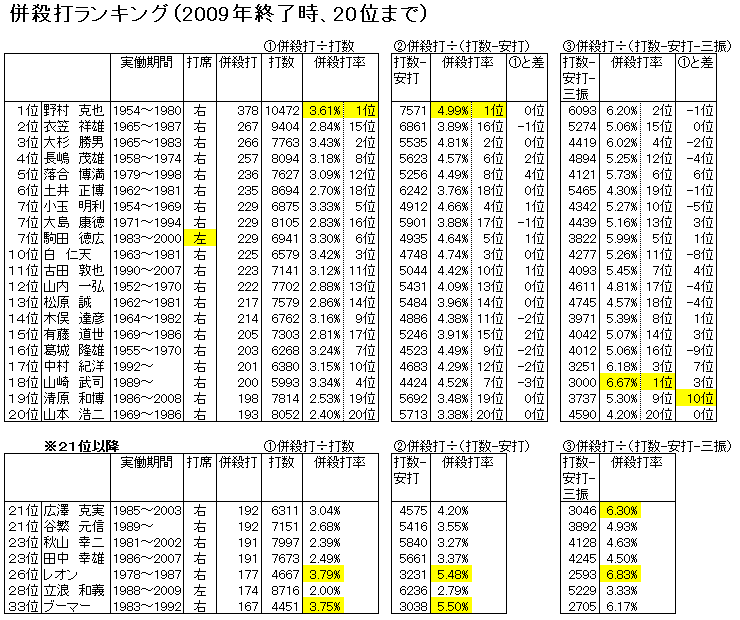第12回 第7回のその後(データの更新と修正)(2010.09.27)
7年以上前、第7回で『右』の強打者の宿命というタイトルで、右打ちの強打者には併殺打のリスクが付き纏うということを述べた。
そのページ内で通算併殺打の20位までを掲載したが、最近になってこの表を見返した時に、「2003年当時に現役だった古田敦也は何位まで順位を上げて引退したのだろうか?」という疑問がわいてきた。
古田敦也の引退は2007年。数値が上下に変動する打率と違って、増え続けるしかない併殺打が引退までの5シーズンでどこまで増えたのか?
そこで、2009年終了時においての通算併殺打の上位20人のデータ更新をおこなった。それが下の表である。
この7年間で1位から10位には変化はなかったが、下位では清原和博や現役の中村紀洋・山崎武司の楽天コンビがランクインしている。
ついでに併殺打率の見直しもおこなったのだが、7年前にとんでもない間違いを犯していたことがわかった。
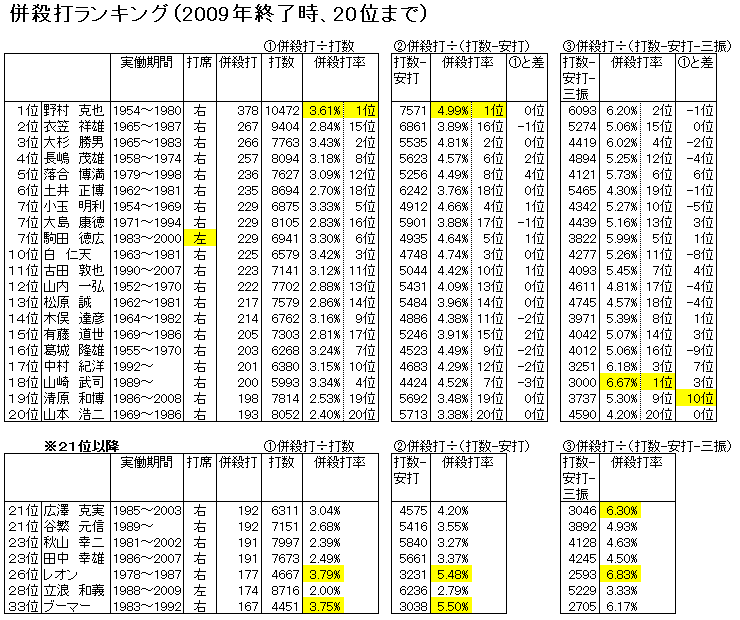
最初に、自分が知りたかった古田敦也について述べる。
2002年終了時に185で20位だったが、5年間で223まで積み上げ11位で現役を終えた。
そして、今回のメインである併殺打率。計算式は、併殺打÷打数なのだが、7年前との違いがわかるだろうか。
実は、駒田徳広の打数を間違えていたのである。あれだけ「駒田の併殺打率が高い」と力説していたのに、非常に情けない。なぜ間違えたかというと、駒田の打数の最後の1年分が抜けていたのに気づかなかったというごく初歩的なミスのためで、データ管理ができておらずお恥ずかしい限りである。
駒田の併殺打率を正しく計算すると、併殺打率の順位では6位(7年前だと5位)なので左打者であることを考えれば高いのだが、2位と5位とではインパクトに欠けるのは否めない。第7回をページごと削除しようかと思ったが、反省の意味をこめて、削除も修正もせずにそのまま残すことにする。
改めて併殺打率の順位を見ると、駒田が下がった分、他の選手の順位が繰り上がり、大杉勝男が2位になった。また、現役の山崎が4位に食い込んでいるので、引退までにこの率がどう変動するか注目である。
これ以降の内容は数字遊びとしてご覧いただきたい。
併殺打率の計算にあたり、分母は打数にしたが、打数には安打が含まれているので、安打の大小(=打率の高低)が併殺打率に影響するのではないかと思い、打数から安打を引き算したものを分母として計算してみた。それが上の表の②の部分である。分母が小さくなるので併殺打率は大きくなるのだが、①と比較しても相対的な順位では大きな変化はなかった。
続いて、さらに三振も引き算したのが上の表の③の部分である。
打数から安打と三振を引き算することで、「バットにボールが当たった凡打」に占める併殺打の割合を求めることができると考えたのである。
これで計算すると、野村克也を抜いて山崎が1位になった。また、①から大きく順位を上げた(5位以上)のが清原(19位→9位)、中村(10位→3位)、落合博満(12位→6位)である。
これら3人はボールに当たれば併殺打になる割合が高かったわけだが、この③での評価は非常に難しい。ボールを当てる技術のある(三振しにくい)打者には不利になることもあるからだ。ボールを捉える技術があるばかりに、当たり損ないが併殺打になることも多いので、この率が高いからといってゲッツーマシーンという評価を下すのは危険な気がする。
また、①②③の全てに当てはまることであるが、走者の有無によっての打数の不公平が大きく、本格的に調べる(評価する)のであれば、無死または1死で1塁において走者を置いた機会、つまり併殺打が起こる条件だけを分母にして計算するべきだろう。まあ、そのようなデータを手に入れるのはほぼ不可能なのだが・・・。
参考データとして、21位以降で何人かピックアップしてみた。
21位タイには現役の谷繁元信がおり、今シーズン終了後には20位以内に入るのは間違いない。
28位には昨年で引退した立浪和義が入っているが、駒田以来となる2人目の左打者である。立浪の場合は、
(A)現役期間が長かった。 →22年は、通算併殺打の上位30人の中で5位タイ(秋山幸二や田中幸雄と同じ)。
(B)打数が多かった。 →8716打数は、通算併殺打の上位30人の中で3位、上位40人に広げても5位。
(C)1番打者として打つ機会が多かった。 →正確なデータはないが、「1番ショート」「1番セカンド」の期間が長かった。
などの条件が重なったためと考える方が良いだろう。
立浪の①の併殺打率を見ると、2.00%で誰よりも少ない割合になっているが、これは1番を打つことが多かったゆえの打数が含まれていることが大きい。
年間144試合(20年ぐらい前なら130試合)あるとして、全ての試合に1番打者としてスタメンに入るとすると、初回の第1打席は必ず無死無走者の状況(併殺打が絶対に起こらない状況)で打席に入ることになる。考えるまでもなく、それらの144打数(実際は四死球で出塁することもあるので打数はこれよりも少なくなるが)も分母に含めれば公平な比較はできない。
やはり、上で述べたように、併殺打率を比較するのであれば、併殺打が起こる条件だけをピックアップして分母にするべきだろう。
個人レベルだと、ここまでが限界ということで、データを手に入れることができる方(雑誌社、スポーツ紙関連?)にはぜひ調べてほしいものである。結構、面白いと思うのだが・・・。
26位と33位にはレオンとブーマーが入っているが、この2人の併殺打率が凄い。
①と②で見ても、1位の野村を上回っているのである。分母の問題があるので、この数値を鵜呑みにはできないが、野村よりも上というのは意外だった。3人とも3〜5番を打つことが多かった右の強打者だが、走力の差が原因(野村117盗塁、レオン28盗塁、ブーマー18盗塁)の1つと言えるかもしれない。
ブーマーは打点王を獲った年は併殺打もリーグ1位という珍記録の持ち主だが、レオンもブーマーも長打力と確実性があったわけで、試合に多く出る以上、併殺打率の高さだけを取り上げて言及するのはデータの見方として正しくないであろう。そもそも併殺打だけが多い打者なら、10年間も日本球界にいないからである。
以上、7年前のミスがあったというお粗末な内容であったが、新たな発見もあったということで、今後も不定期ではあるが数字いじりを続けていきたいと思う。
また、手に入るデータを無理矢理に加工して出した数値なので確実性に欠ける部分が多く、文末が「・・・だろう」「・・・かもしれない」という表現が多くて読みづらくなったこと、丸数字の機種依存文字を使ったこと(Macユーザーの方、申し訳ございません)も併せてお詫びいたします。
プロ野球記録回顧部屋に戻る